100円ライターの処分に困った!を解決する記事です。
はじめに
こんにちは!
アンドレです。
先日、断捨離をしていたらたくさん出てきた使い捨ての100円ライター。
ずいぶん溜め込んでしまっていました。2個くらいあれば十分なので他のものは捨ててしまいたいのですが...
ちゃんとガスを抜いてから捨てないと危ないな
でも7個かぁ
ちょっと面倒だなぁ
確実で効率的な処分方法はないかなー
と模索していたわけですが、私なりに答えを出しました。
確実にガスを抜き、なおかつ安全かつ効率的な処分方法を私なりに断定しましたので、ここに紹介します。
写真付きで解説します。
「破壊」以外のガス抜き方法、処分方法も解説します。
少しでもだれかの参考になれば嬉しいです!
結論:破壊(物理的に壊してガスを抜く)
結論、
「 破壊 」
です。
いたってシンプルなわけですが、これに尽きるな、といったところです。
「はじめに」の黄色マーカーのところに「安全」と書きましたが、「ライターを破壊するのは危険では?」と思った方もいるかもしれません。ここで言っている「安全」には二つの意味合いがあります。
ひとつは、「ちゃんと対策をすれば安全に処分できる」という意味。対策自体は簡単で、屋外でやるとか濡れたタオルで包むとかそういった簡単な対策です。そうすれば安全に処分できるよということです。
もうひとつは、「ゴミ収集の作業員の方々、ゴミ処理場への安全配慮」です。「ガスを抜ききって...」と言われても、ガスは目に見えないので抜けたか抜けていないのかイマイチはっきりしません。そんな状態で捨てるのが私にはどうもしっくりきませんでした。目で見てはっきりとガスが抜けていることが分かれば、捨てる不安もなくなるし、ゴミ収集の人たちも処理場も安全に処分できると思ったわけですね。
そのあたりも考えた上で、自分で破壊してしまった方が最適解だと考えました。
やりかた
1 濡らしたタオルを準備する
2 ハンマーを準備する
3 火の気のない風通しの良い屋外に出る
4 マスクと保護メガネをつける
5 処分したいライターを濡らしたタオルで包む
6 あらためて周囲を確認する(火の気は本当にないか、換気は良いか、人がいないか等)
7 タオルで包んだライターを地面に置いてハンマーで叩く
8 自治体に従って燃えるor燃えないゴミとして出す
百聞は一見にしかず。
ということでさっそく簡単な説明文と写真を載せていきますね。
場所は屋外。
準備するものは、
・処分したいライター
・濡らしたタオル
・ハンマー

処分したいライターを濡らしたタオルで包みます。ただ包むというより上下左右まるっと包み込みましょう。ハンマーで叩き割って隙間から飛散したら危ないからです。

タオルの上からライターめがけてハンマーで叩き割ります。

ライターのガス充填部が割れました。ということはガスが放出されたということですね。細かい部品までバラバラになりました。

あとは拾い漏れがないようにちゃんと回収して、お住いの自治体に従った方法で捨てれば完了!
以上です。
上に載せた写真では砕石(砂利)の上で叩いていますが、力が分散してしまい、スムーズに割ることができませんでした。アスファルトやコンクリートのような平らな面で叩くとだいたい一発で叩き割ることができました。
破壊するときの注意点
- ガスを逃がすので屋外でやりましょう。
- 火の気がないところでやりましょう。
- 危ないのでマスクと保護メガネ(ゴーグル)をしましょう。
- 作業用の手袋があればGOOD!
- ハンマーで叩き割るので飛散に気を付けてください。
- ライターは不要なタオルなどで包んでタオルの上から叩きましょう。
- 思わぬところから破片が飛んでこないように上下左右を覆うようにしっかり包みましょう。
- タオルはしっかり濡らしておくこと。ビチャビチャで構いません。
- ポンッ!と破裂音がするので、周囲に迷惑がかからないよう注意しましょう。
- 万が一、発火してしまったときのために水バケツがあるとGOOD!
点火レバーなどが壊れてしまいガス抜きできないときに、ハンマーで叩き割るこの方法がよく話題にでます。
本来、主流は下記に書いた「輪ゴムやテープを使ったやり方」です。
個人的には、処分したいライターがたくさんあるときは破壊してしまった方がはるかに効率的だなと感じました。
破壊以外の処分方法
破壊する方法は危なっかしいし、少し怖いと思う方もいると思います。
穏やかにガス抜きをする方法もあるので紹介します。割らない方法です。
・輪ゴムを使ってガス抜きする方法(左)
・テープを使ってガス抜きする方法(右)
(下の写真のようなやり方です)


具体的なやり方
1 輪ゴムやテープを準備する
2 火の気のない風通しの良い屋外に出る
3 点火レバーを押す(押し続ける)
4 着火したときは息を吹きかけ火を消す
5 輪ゴムやテープでレバーが押された状態を固定する
6 「シュー」とガスが抜けていることを音で確認する
7 音がしない、小さいときは火力調整レバーが最大になっているか確認して調整する
8 半日以上、放置する
9 再度着火操作をして火がつかないことを確認する
10 万が一のことを考え、濡らしたタオル等で包んでから自治体に従った方法で捨てる
私はセロテープを使ってみて「固定力がいまいち足りないな」と苦戦しました。
ガムテープを紹介している記事がありましたが、確かにガムテープの方が固定力が高そうです。
ガムテープを持っている方はぜひお試しください。
ちなみに輪ゴムを使ったやりかたもコツが必要です。
うまくセットしないと飛んでいってしまいます。
それぞれ実際にやってみた感想は、
・処分したいライターがたくさんあるときは、ひとつひとつを対処するのが手間
・CR機能(こども対策)付きライターはレバーを下げたまま固定するのが大変
・確実に、完全にガスが抜けているか少し不安
でした。
まとめ
ライターの処分は少し手間がかかって面倒です。
でも、テキトーに捨ててはいけません。
ゴミ収集車やゴミ処理場で火災がおき、ゴミが収集されなくなって困るのは本人や近隣の人たちです。
もちろん作業員の方たちを危険にさらすことにもなります。
偉そうなことを言って恐縮ですが、ルールを守って正しく捨てましょう。
ライターの処分方法は自治体によってかなり様々です。
例えば、
・東京都豊島区
金属・陶器・ガラスゴミ(ガスを完全に抜いて、袋に「キケン」などと表記する)
・東京都江東区
燃やさないゴミ(ガスを完全に抜き、穴などあけない)
・千葉県習志野市
有害ゴミ(ガスを完全に抜き、水に濡らす)
・茨城県水戸市
有害ゴミ(ガスを完全に抜き、中身が見える袋に入れる)
・埼玉県春日部市
危険ゴミ(ガスが残っている場合、「中身入」を表示して、危険ゴミ専用カゴに入れる)
・埼玉県川越市
可燃ゴミ(ガスを完全に抜いて出す。ガス抜きできない場合は「有害ゴミ」として出す)
などなど、本当にそれぞれ。
お住いのルールを必ず確認しましょう。
また上に書いた例は2025年8月ごろに確認したもので、ご覧いただいている頃には変更があったり古い情報になっているかもしれません。最新の情報を確認するようにしてください。
正直に言うと自治体によってこんなにも違うとは思っていませんでした。
この記事を書くにあたって、こんなにも様々なんだと知りました。勉強になります。
引越しをしたときなどは特に注意したいですね。
ちなみに私が住んでいるつくば市では
「必ずガスを抜き、燃やせないゴミとして出すこと」
がルールとなっています。
確認事項がたくさんあって大変ですが、ルールをしっかり守って正しく処分しましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
おしまい。
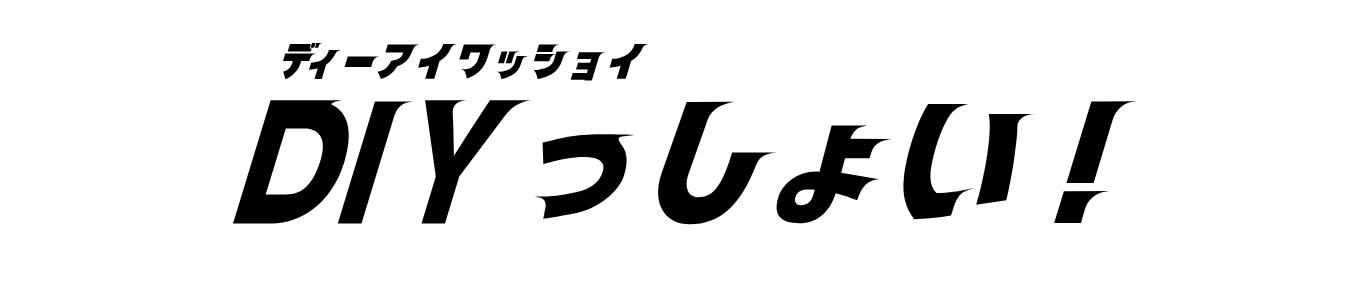



コメント